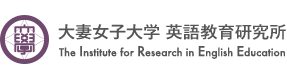服部孝彦
夏号は英語にも相手を気遣う丁寧な表現と相手を不快にさせてしまう失礼な表現があることを学びました。夏号と秋号は世界中の全ての言語における会話に共通する原則と、その原則を破ることによって伝えることができる丁寧表現の仕組みにつて学習しましょう。丁寧表現の学習は、よい対人関係を構築・維持するためには必要ですので、ぜひ理解しておきたい内容です。
私たちは日常、何も意識せずにごく普通に会話を交わしています。この会話には、日本語であろうと英語であろうと世界中の全ての言語に共通したルールがあるのです。この会話のルールを提唱したのは言語哲学者のグライスという人です。グライスはこのルールを「協調の原理」と名づけました。「協調の原理」は「量」、「質」、「関連性」、「話し方」の4つで構成されています。
1つめのルールである「量」は、話し手が話す量は多すぎても、少なすぎてもいけないということです。2つめのルールである「質」は、話し手が話す内容は真実でなければならないということです。3つめのルールである「関連性」は、話されている内容は関連がなくてはならないということです。4つめのルールである「話し方」は、あいまいな話し方をしてはならないということです。
グライスは会話がこの4つのルールに常に従うべきだと主張するために「協調の原理」を提唱したのではありません。むしろその逆で、通常は無意識に従っている「協調の原理」に反することで、会話に「言外の意味」を持たせることができることを理論的に整理するためにこの「協調の原理」を示したのです。
この4つのルールで「言外の意味」を伝えるということで大切なのは3の「関連性」です。次のAとBの二人の対話をみてみましょう。
A: How many kids do you have?
B: My daughter is seven years old.
Aが子どもは何人いるかと尋ねているのに対してBは質問とは関連性のない娘の年齢を答えています。これは「関連性」のルールに違反していますのでこの場面ではAとBの会話は成立しておりません。しかし、実際の会話ではBがわざと「関連性」のルールに違反し、そのことによって「言外の意味」を伝え、相手に対して丁寧であろうとすることもあるのです。次のCとDの二人の対話をみてみましょう。
C: How about going to the new Indian restaurant for dinner tonight.
D: Well, actually I had lunch at that restaurant today.
Cが新しく開店したインド料理のレストランに夕食を食べに行こうとDをさそっているのに対して、Dは行きたいとも行きたくないとも答えず、Cの言ったこととは関連性のない、自分は今日昼食をそのインド料理のレストランでとったという事実のみを述べています。Dはわざと「関連性」のルールに違反することにより「言外の意味」を持たせ、Cのインド料理のレストランに行こうというさそいを丁寧に断り、別のレストランにしようと伝えているわけです。「協調の原理」にわざと違反することにより生じる「言外の意味」のことをグライスは「会話の含意」とよんでいます。