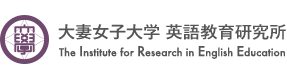Education and Entrance Exam Reforms
今月の雑テーマは「教育・入試改革のゆくえ」です。林芳正文部科学相は、「中央公論」における藤原和博奈良市立一条高等学校校長との対談で、2020年度から実施される大学入試制度改革など一連の教育改革について基本的な考え方を明らかにしました。 精神科医の和田秀樹氏は、教育改革について「日本の受験生の学力とメンタルヘルスに危険な影響を与えかねない」としていくつかの問題点を指摘しています。〝主体的な学び″を重視する改革は、『ゆとり』派の巻き返しであるとするとともに、関心や意欲、思考や判断などの〝観点評価″、さらに面接、小論文の重視は、客観的評価が難しく、最大の問題点は「公平性が担保されないことだろう」と指摘しています。 また、明治大学の齋藤孝教授は、竹内洋・関西大学東京センター長との「中央公論」での対談で、新しい学力として問題発見・問題解決型の学力が求められているが、「知識重視・暗記中心型の従来型の学力も大事」と強調しています。その例として医学部での6年間の教育は「実習を除けば90%以上が暗記に費やされている」と指摘しています。日本語と英語の記事を比較しながら、皆さんの英語学習に役立ててください。上手な英訳です。
日:http://fpcj.jp/j_views/magazine_articles/p=62834/
英:http://fpcj.jp/en/j_views-en/magazine_articles-en/p=62839/
Arguments Calling for a Revision of the Three Non-Nuclear Principles
秋の深まりとともに、世界のニュースは、ジンバブエ、ロヒンギャ、シリアと目まぐるしく移り変わり、北朝鮮の核をめぐる緊迫した情勢はかなり薄らいだ気がしないでもありません。しかし、11月20日には、アメリカが北朝鮮をテロ支援国家に再指定しましたし、今は「嵐の前の静けさ」なのでしょうか?他方で、北朝鮮の核問題のために、日本の核武装に関する国際的なメデイアの議論も見られるようになっておりますし、日本国内でも「非核三原則」に見直しを迫る議論が行われています。もはや日本の核武装を議論することは、以前ほどタブーでなくなっていると言っていいかもしれません。石破・元防衛相、加藤良三・元駐米大使、渡部恒雄・笹川平和財団上席研究員等による議論を、英語でお読みください。
http://fpcj.jp/en/j_views-en/magazine_articles-en/p=59811
“America First” and Its Implications
11月5日から7日まで、トランプ米大統領が訪日しています。タイミングよくフォーリン・プレスセンター理事長、赤阪清隆氏(元国連日本代表部大使)が、「アメリカファーストとそのインプリケーション」と題して、一橋大学大学院で講義を行い、そこで使用されたパワーポイントを本研究所所長の服部教授が入手いたしました。赤阪氏の許可を得ましたので、ぜひパワーポイントをお読みください。講義は英語で行われたため、パワーポイントも英文の多いスライドとなっております。
TPP、パリ協定、ユネスコからの離脱など、トランプ大統領が次々と打ち出してきたアメリカファーストの政策は、確実にリベラル国際秩序に深刻なダメージを与えつつあると思います。そこで、日本としてはどう対処すべきかですが、赤阪氏は、スライド最後から2番目の三浦瑠璃さんが提唱する強硬策(核武装を含め)よりも、最後のスライドの船橋洋一さんの中国との協力を含む積極的な穏健策に共感を覚えると話しております。本学学生の皆さまはどのようにお考えでしょうか?
“America First” and Its Implications
Will India Manage to Overtake China?
中国の共産党大会で、習近平総書記は、21世紀半ばまでに、中国を米国と並び立つ強国にする構想を発表したと報じられています。他方、テイラーソン米国務長官は、10月18日、来週のインド訪問を目に、「インドは他国の主権を尊重する枠組みの中で行動しているのに対し、中国の南シナ海での挑発的なふるまいは国際法や規範に挑むものだ。法に基づく秩序への中国の挑戦にひるむことはない」と、中国を名指しで強く批判したとのニュースが入っています。今回は、「中国を追うインド、その行方は?」をテーマにした中国とインドとの関係に関する記事です。英文で詳しい内容を読んでみてください。
http://fpcj.jp/en/j_views-en/magazine_articles-en/p=59131/
Nursing Care for Seniors and Seniors in the Workforce
今回は「高齢者介護の問題と、シルバー人材の活用」についての英文の記事を紹介します。 一時は入居待機者が52万人にも上っていた特別養護老人ホーム(特養)が、最近では「入居者が思うように集められず、各地で定員割れを起こしている」とのことです。他方、高齢者の生きがいのために、市区町村単位に設置された社団法人で、自治体の60歳以上の居住者が登録し安価で仕事を引き受けるという「シルバー人材センター」の活動が活性化し、各地のユニークなサービスが成果を挙げているようです。詳しくは下記の英文でお読みください。
http://fpcj.jp/en/j_views-en/magazine_articles-en/p=60304/
Will an Age of Electric Vehicles Arrive?
今回は、「電気自動車の時代が来るのか?」というテーマを扱います。今から20年前、地球温暖化防止のための京都会議が開かれた時点では、自動車の将来については、(1)燃料電池車、(2)ハイブリッド車、(3)電気自動車などについて識者の意見が大きく分かれていました。その後のハイブリッド車の発展ぶりは予想を超えたものでしたが、今や、「これからは電気自動車の時代」という声が大きくなってきました。
環境ジャーナリストの小澤祥司氏は『世界』の記事で、電気自動車(EV)が次世代エコカーをめぐる競争で前面に一気に躍り出た背景について、①仏英両国が2040年までに化石燃料車販売禁止を打ち出した②中国が2019年から自動車メーカーが製造・販売する(輸入を含む)乗用車の10%を新エネルギー車(NEV)とすることを義務付けた、ことが大きな要因だと指摘しています。表面的には気候変動対策などが理由ですが、その実態は「次世代自動車市場における主導権確保の狙いがある」と分析しています。
詳しくは、以下の英文記事をお読みください。
http://fpcj.jp/en/j_views-en/magazine_articles-en/p=61072/